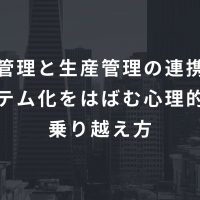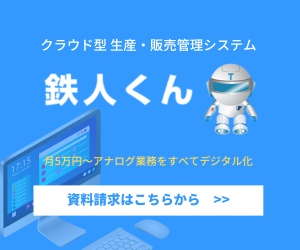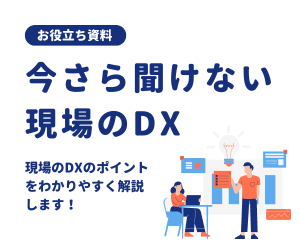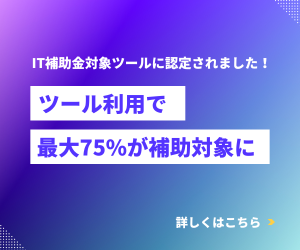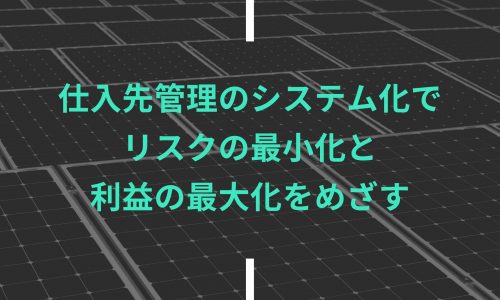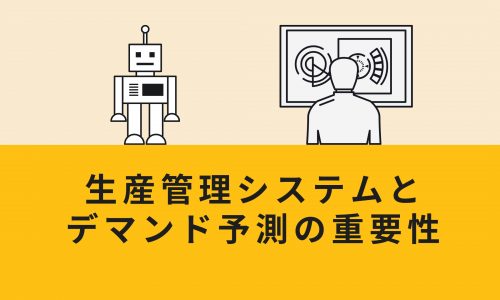製造業界では、急速な技術革新やグローバル競争の激化により「リスキリング」が注目されています。しかし、リスキリングを進める際には、様々な課題や障壁に直面するのも事実です。本記事では、製造業のリスキリングで失敗しないために必要な5つのステップについて解説します。
製造業のリスキリングで失敗しないために必要な5つのステップとは?
急速な技術革新やグローバル競争の激化で、製造業では従業員のスキルアップが必要とされています。従来の製造スキルだけでは対応が難しくなってきていると感じている人も多いでしょう。
こうした状況で注目されているのが「リスキリング」です。製造業にとって、リスキリングは単なる人材育成の手段ではなく、事業の継続と発展に欠かせない戦略的な取り組みです。しかし、製造業でリスキリングを進めるには、様々な課題があります。一般的な教育プログラムを導入しても製造現場にあわず、うまくいかないケースが少なくありません。
本記事では、製造業のリスキリングで失敗しないために必要な5つのステップについて解説します。製造業特有の課題を踏まえながら、効果的なリスキリング戦略を立てるためのポイントを詳しく見ていきましょう。
リスキリングとは
リスキリングとは、学びなおしを指す言葉で、職業で必要な能力を再開発することを意味します。 近年では産業のIT化にともない、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略においてのリスキリングが注目されています。
日本政府が、2023年6月に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」でも、労働者のスキルアップを促し、成長分野への労働移動を円滑にしていくことで、日本企業と日本経済の成長を促す方針を示しています。
「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、
- リスキリングの支援金の半分以上が個人経由での給付が可能となるよう直接支援を拡充
- 教育訓練給付の拡充や教育訓練中の生活を支えるための給付と融資制度の創設を進める
- 失業給付制度において自己都合の離職で失業給付を受給できない期間、失業給付の申請前にリスキリングに取り組んでいた場合は会社都合の離職と同じ扱いにする
などの案が示されています。
製造業にとってのリスキリングとは?
「政府がリスキリングと言っても、ピンとこない」「生産に忙しいのに、それどころじゃない」など、製造業からはリスキリングに対して否定的な声も聞かれます。
では、日本のものづくりにとって、リスキリングはどのような意味をもつのでしょうか?
変化する「ものづくり」
世界では、ITを活用したサービスを展開し、IT業界で支配的、独占的にビジネスを展開しているGAFA(Google・Apple・Facebook・Amazonの頭文字を組み合わせた造語)は、従来のものづくりとデジタル技術を融合させて急成長しています。
いままで、ものづくりを行ってきた企業も今後の成長を目指すには、データを利活用して、より、効率的でニーズに合ったものづくりを軸とした企業への転換が必要になっています。
注目される機械エンジニアのリスキリングとは?
現在製造業で注目されているのは、機械に特化したエンジニアをリスキリングして、ソフトウェアエンジニアリングやデータサイエンティストへ転向させる事例です。元々、理論的な考え方が得意な人材はデータサイエンスになじみやすく、本人要望にも合致しやすいこともリスキリングが活発な要因でしょう。製造業のDXにもマッチした人材戦略が、多くの企業で行われています。
リスキリングが製造業にもたらすもの
リスキリングは、製造業に必要不可欠ですが、具体的にメリットをあげてみましょう。
既存社員のスキルアップ
製造業においてDXを確実に進めるためには、現場での能力とデジタル技術の両面に精通した人材が不可欠です。リスキリングによって、社内でDXを推進できる人材が確保できれば、企業秘密を他社に知られるリスクなしに、業務の工場が可能になります。
人材流出の防止
リスキリングの機会を提供すれば、従業員のモチベーションと企業への信頼が高まります。従業員のキャリア開発を支援する取り組みは、会社に自分の成長を支援してもらっていると感じます。その結果、企業への帰属意識が向上し、他社への流出が防げるでしょう。優秀な人材の定着率が高くなれば、組織は安定し継続的な成長につながります。
企業イメージの向上
リスキリングへ積極的に取り組む企業は、従業員の成長を重視し、改革に前向きなイメージをもたれるでしょう
優秀な人材の確保
優秀な人材ほど、成長できる機会のある企業を選ぶ傾向があり、リスキリングに力を入れる企業は、求職者から魅力的に映ります。特に、若手の人材はスキル開発を重視する傾向があるので、優秀な新卒採用にも有利になるでしょう。
組織の活性化
リスキリングは、組織の活性化にも繋がります。新しいスキルを習得した従業員は、業務に新たな視点やアイデアをもたらす存在です。業務プロセスの改善や新しいソリューションの開発も可能になるでしょう。
また複数の職務を遂行できるスキルを身につければ、部門間の連携も円滑になり、全体最適な働き方が可能になります。「学び続ける組織」という文化が根付けば、変化に適応し、常に改善を図る組織づくりにつながります
製造業でリスキリングが進まないのはなぜ?
リスキリングが必要不可欠だと思って始めたのに、うまくいかない。それには、どんな要因があるのでしょうか?
従来のスキルへ依存してしまう
長年培ってきた技能やノウハウで、ある程度効率的に生産ができていると、新しいスキルの必要性を感じにくく、従来のスキルに依存しやすくなります。
特定の職務に特化した人材が多い職場だと、何十年も同じ仕事をしている人もいます。これは「人に仕事がついている」状態で、企業の継続を考えると重大なリスクです。
優先度が低くなりがち
製造業は、目の前の生産性や効率性が重視されやすい傾向があります。リスキリングの効果は、すぐに目に見える形で現れにくいので取り組みへの積極性が低くなりがちです。
生産ラインを止められない、人手が足りないといった要因が、リスキリングの実行を妨げることもあります。
リスキリングが必要なのかわからない
急速な技術革新やビジネス環境の変化は、日々報道されていますが自分の仕事には直接関係ないと考えてしまうことがあります。
これは、 現在の職務に満足し「今のやり方で十分」「今の仕事で満足」と思っているのかもしれません。年齢が高い従業員ほど、新しいことを学ぶことへの抵抗感を持ち「自分にはできない」「このまま定年まで」と思いがちです。
また、社内でリスキリングが実施されていないと、従業員のリスキリング意欲も高まりにくいでしょう。
製造業でリスキリングを行う際のポイント
製造業でリスキリングをする際に注意することをまとめました。
トップダウンで実施する
製造業では、現場の生産性や品質が重視される傾向にありますが、リスキリングを進めるには、トップダウンで行うほうがスムーズです。
トップダウンでリスキリングを推進すれば、経営の方向性に合わせたスキル開発が可能になります。従業員はリスキリングが全社的な取り組みとしてすすめられているのだと認識するでしょう。
トップが率先して学び続ける姿勢を示せば、従業員の意識改革につながり、大きな成果を生み出すことができるでしょう。
長期の視点を取り入れる
リスキリングは、短期で成果が出るものではなく、一貫性のある取り組みを長期的に続ける必要があります。また、会社の事業戦略と連動させたリスキリングの計画を立てれば、計画的な人材開発が可能になるでしょう。
継続的に取り組めば、スキルアップした従業員が、後輩の育成に携わることも可能です。このことで、ノウハウや仕事への姿勢や考え方も継承されます。
実務も利用する
製造業のリスキリングは、実務との連動が不可欠です。実践を取り入れながら、業務に即したスキル開発が成功のカギを握っています。学んだスキルをすぐに業務に活かし成果を実感できれば、スキルの定着にも繋がり達成感によってモチベーションが高まります。
先輩社員による指導や、業務を通じた学習機会を提供することも大切です。話し合いながら学べば、先輩社員の学びにもつながり、現場の具体的な課題に対応したスキルが身につくでしょう。問題解決の機会にもつなげられるかもしれません。
評価する仕組みを作る
評価の仕組み作りは、リスキリングを効果的に進める上で欠かせません。評価の仕組みを作れば、目標がどれくらい達成できたかが明確になり、公平性が確保できます。
また、このことによって組織全体のスキルの状況が把握できます。どの分野で強みがあり、どこに課題があるのかを知れば、今後のリスキリング計画に反映できるでしょう。評価をフィードバックすれば、従業員の成長と組織の発展につながります。仕組みを作れば、わかりにくいリスキリングの成果も、定量的に提示できます。
リスキリングを成功させる最初の5ステップ
製造業がリスキリングを成功させるための5つのステップを順に説明します。
1. スキルを明確化する
リスキリングを始める前に、まず必要なスキルを明確にしましょう。
従業員が、どんなスキルをもっていて、どのようなレベルなのかをあげます。作成には各工程の社員の意見も必要になるでしょう。
スキルリストは大まかなスキル分類の下に、できるだけ具体性を持った項目まで分解した項目を設け、評価が明確にできるよう数値化して作成します。
2. 自社の戦略を設定する
将来必要となるスキルとのギャップを特定します。技術革新の動向や、競合他社の状況なども考慮に入れて、優先的に習得すべきスキルを選定します。
戦略に合わせて、スキルリストの優先順位を設定します。
3. ゴールを設定する
リスキリングを優先順位をもとに、習得すべきスキルの到達レベルや、期限などリスキリングのゴールを具体的に設定します。
このとき「○○ができるようになる」などといった個人のゴールと「○○のスキルがレベル3の社員が何人」といった組織全体のゴールの両方を設定することが大切です。ゴールは、現実的な内容だけではなくチャレンジ精神を持ち合わせたものが必要です。
4.道筋をつける
ゴールを達成するためのマイルストーンとなる小さな目標を置き、リスキリングを実施する目安となる道筋をつけます。スキル習得のための研修プログラムや、実務を通じた学習機会など、具体的な内容にしましょう。従業員一人ひとりのキャリアプランにも即した個別の育成計画が必要です。
5.共有する
リスキリングの取り組み内容を組織全体で共有します。経営層から従業員にまで、実施するリスキリングの目的を理解し、協力できる体制を作ります。それまで達成に消極的だった従業員も、自らの計画を共有すれば「やらざるをえない」という気持ちになるかもしれません。
定期的な進捗を報告したり成果を共有したりすれば、モチベーションが維持できます。
伴走で成功率が上がる
リスキリングを成功させようと思うなら、リスキリングの計画を作り提供するだけでは不十分です。従業員に寄り添い伴走しなければ、成功率は下がってしまいます。
まず、計画の段階で一人ひとりのスキルレベルや学習状況を把握し、個別の目標設定やカリキュラム作りを支援します。リスキリングは、定期的にフォローアップし、困りごとを解決するサポートや、実務での実践機会を提供する働きかけが必要になります。
スキル習得後も、スキルの活用状況や次のスキルの取得目標の提供など、成長を見守りましょう。全プロセスにおいて伴走し、寄り添いながら成長を後押しする姿勢が、リスキリングの成功率を大きく高めます。
リスキリングは永続的な取り組み
技術革新のスピードが加速する中、人材育成は製造業の喫緊の課題です。失敗の要因も多い中で、製造業がリスキリングを成功させるためには、①スキルを明確化する②自社の戦略を設定する③ゴールを設定する④道筋をつける⑤共有するの5つのステップを大切にするとスムーズです。このことで続けていける体制も整います。
効果的なリスキリング戦略を立てるためには、製造業特有の課題を理解し、それに適したソリューションを見つけることが欠かせません。そこで、製造業専門のクラウド型生産管理システム「鉄人くん」の活用がおすすめです。製造業界で扱う膨大な物品を一括管理できる鉄人くんなら、リスキリングに必要な情報の整理や進捗管理がスムーズに行えるはずです。製造業のリスキリングは一朝一夕にはできませんが、5つのステップを着実に進め、寄り添いながら変革に繋げていきましょう。
トライアルキャンペーンも実施していますので、生産管理システムの導入を検討してみたいとお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。
この記事を通じて、製造業の経営者、現場責任者、DXやIT担当者の皆様にとって、不明点の解消やポイントの理解に繋がり、実際のプロジェクトに活用していただければ幸いです。