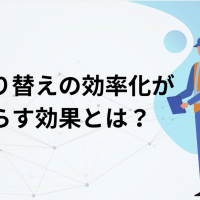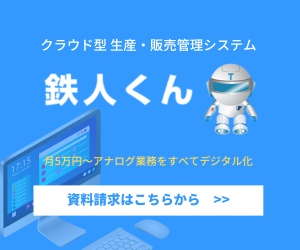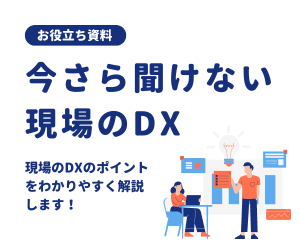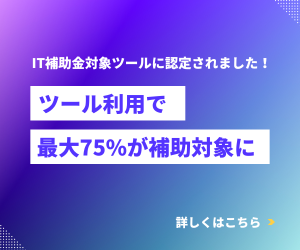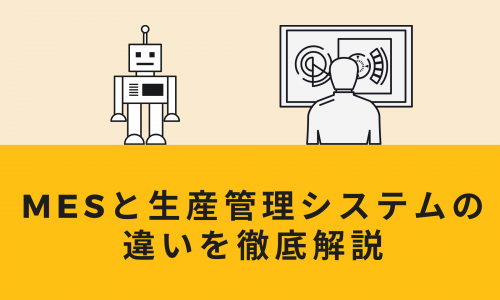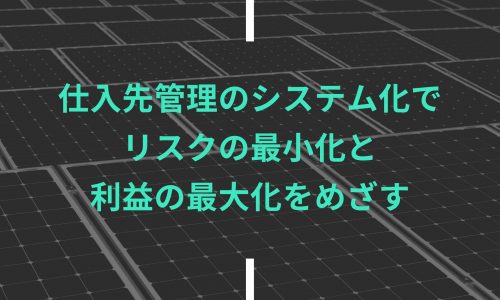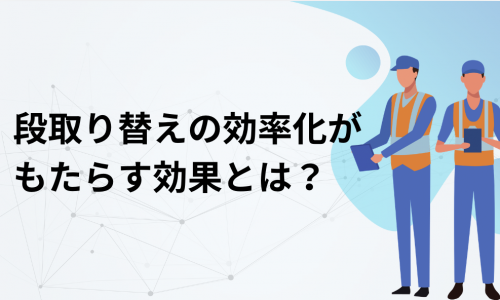製造業の経営者や現場責任者として、「工程ごとにどんな資源を使い、誰がどんな手順で作業し、どう評価すればいいのか」をスムーズに把握できず、品質トラブルや納期対応に追われていませんか?
現場ではベテランスタッフのノウハウが属人的になっていたり、外部監査や顧客からの要求に合った文書化が追いついていなかったり……。そんな悩みを抱える方にぜひ知っていただきたいのが「タートル図」という手法です。
本記事では、タートル図が製造現場にもたらすメリットや基本的な作成・運用のポイントを分かりやすく解説します。品質向上や生産性アップを図りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.タートル図の基本概念と導入の背景
タートル図とは、品質マネジメントシステム(QMS)の文脈で広く用いられる可視化手法の一つで、「プロセスを構成する要素を見える化し、品質や生産性を向上させるために活用する」ことを目的とした図表です。英語圏では「Turtle Diagram」とも呼ばれ、その名のとおりカメ(タートル)の形状になぞらえたレイアウトが特徴的です。具体的には、中央にプロセス(やるべき作業の塊)を配置し、左右・上下に「Who(誰が)」「With what(何を使って)」「How(どのように)」「Measures(成果指標は何か)」などを振り分ける構成になっています。カメの甲羅部分に「プロセス」を置き、頭や足の部分がプロセスを支える各要素を表すイメージです。
● タートル図の目的と効果
ISO 9001やIATF 16949などの国際規格では、「プロセスアプローチ」が重要な原則として掲げられています。これは品質保証だけでなく、生産管理やコスト削減、納期遵守などを達成するために、各工程を切り出し、それぞれがどのように運営されているかを明確にするやり方です。タートル図は、このプロセスアプローチを具体的に落とし込むための便利なツールとして普及しています。
大きなメリットは以下の通りです。
-
可視化による理解促進
プロセスを一枚の図にまとめるため、現場スタッフや経営層にとっても直感的に理解しやすい。複雑な業務であっても「カメの甲羅」に収まる形で整理すれば、どこに必要なリソースがあって、どこが弱点になっているかをすぐ把握できる。 -
課題抽出の効率化
「誰が(人材)、何を使って(設備・ツール)、どのような手順で(手法)、成果指標は何か」を明記することで、プロセスの抜け漏れや責任範囲の不明瞭さを見つけやすい。さらに、問題発生時に「どの要素に原因があるか」を検討しやすくなる。 -
ISO規格へのスムーズな対応
タートル図は国際規格や業界標準の監査でも評価されやすく、監査員がプロセスを確認する際の説明資料としてしばしば活用されます。特にIATF 16949や医療分野のISO 13485などでは、工程ごとの責任者と手段を明確化した文書が求められるため、タートル図がそのニーズに合致する形です。
● 製造業における導入の背景
現在、製造業は多品種少量生産や短納期対応、品質要求の高度化など、数多くの課題に直面しています。またDX(デジタル変革)が叫ばれる中、従来の属人的・紙ベースの管理手法では追いつけなくなっているのも実情です。タートル図はそうした時代の要請に応えつつ、「まずはプロセスを整理し可視化する」という基本を確実に行うステップとして導入されるケースが増えています。
中には「既に工程表やフローチャートは作っている」という企業もありますが、タートル図はあくまでプロセスを中心に、必要な要素を体系的に配置する点がフローチャートや単なる手順書と異なります。従来の文書化で扱いにくい「資源(リソース)」や「評価指標(Metric)」を同時に俯瞰できるため、管理や改善の議論がすぐに始められるという強みを持つのです。
さらに、各工程の「インプット」と「アウトプット」が明示されることによって、隣り合う工程間での責任分解点も明確化しやすくなります。例えば「このパーツはどの工程から来て、どの工程へ渡すか」や「どう測定して品質を確認するか」が図に反映されるため、工程間トラブルや見落としを防ぎやすいという効果が期待できるでしょう。
2.タートル図の構成要素と作り方:製造プロセスを整理するステップ
タートル図は、カメの形を模して「プロセス」と「プロセスを取り巻く要素」を配置します。その際、各要素をどのように列挙し、どう関連づけるかがポイントです。ここでは、タートル図の典型的な構成要素と、実際に作成する際のステップを解説します。
2-1. タートル図の典型的な構成
-
中央(甲羅): プロセス名
ここに描くのは、今回整理したい製造工程や業務プロセスの名称。たとえば「部品加工工程」「最終検査工程」「購買プロセス」など、対象とする範囲を明確に定義します。カメの中心に大きく書くことで、「この図は何のプロセスを扱っているか」を一目で示します。 -
上部(カメの頭): インプット(入力)
プロセスの入り口となる情報や材料を記載します。製造業の場合、原材料や部品、図面、注文書などが典型的なインプットです。例えば「切削加工工程」であれば、加工するための素材ブロックやCADデータがインプットにあたります。 -
下部(カメのしっぽ): アウトプット(出力)
プロセスを経て生成される成果物や情報を記載します。部品加工工程なら「加工完了した製品」や「検査結果」などがアウトプットにあたります。これにより、「何を得るためにこのプロセスが存在するか」が分かりやすくなるわけです。 -
左側(前足): Who(人・組織)とWith what(資源・設備)
-
Who: このプロセスに関わる役職や担当者、部署など。例えば「製造課の切削担当オペレーター」「品質保証部の検査員」などを挙げる。
-
With what: プロセスを行うために必要なリソース(設備、ソフトウェア、冶具、ツールなど)。工作機械(旋盤・マシニングセンタ)、計測器(ノギス、三次元測定機)などがここに入る。
-
-
右側(後ろ足): How(方法・基準)とMeasure(指標・評価方法)
-
How: 手順書や作業基準、標準作業手順、検査規格など「どうやって作業を進めるか」「品質をどう確保するか」の手段を記載。
-
Measure: パフォーマンス指標や評価基準。例えば「不良率」「タクトタイム」「Cpk(工程能力指数)」「納期遵守率」などで、プロセスの効果を定量的に測るための指標を示す。
-
以上の要素をカメの頭や手足に対応する位置に配置し、中央のプロセスと線で繋ぐイメージで描くと、全体が一つの体系として理解しやすくなるのがタートル図の利点です。
2-2. タートル図作成手順
-
プロセスの範囲を決定
まず、「何の工程を対象にタートル図を作るか」を明確化。工程があまりに大きすぎると要素が多くなりすぎるため、業務フローの中で適度な単位(たとえば「切削加工工程」「溶接工程」「組立工程」など)を選ぶことが大切です。 -
インプットとアウトプットの洗い出し
対象プロセスへ入ってくるもの(材料、情報、指示)と、プロセスが生成する結果(部品や書類)を整理。製造業の場合、品目の型番リストや工程内での中間製品を確認しながら確定します。 -
左側(Who/With what)の整理
このプロセスに従事する人員や部署を特定し、必要なスキルや資格があれば追記します。合わせて設備・工具・ソフトウェアなどのリソースを挙げる。実際に「どの機械を使うか」「冶具は何がいるか」「測定器は何を使うか」などを列挙し、過不足をチェックするのがポイントです。 -
右側(How/Measure)の整理
作業手順、検査基準、規格など「どうやって仕事を進めるか」を列挙します。あわせて品質や効率を測るための指標を決めます。製造業であれば「稼働率」「不良率」「サイクルタイム」「納期遵守率」などが代表的です。ここを曖昧にすると、後から「何のためにやっているのか?」が不明確になりがちなので注意。 -
図として配置・相互関係を示す
カメの形になるように中央にプロセス、上部にインプット、下部にアウトプット、左側にWho/With what、右側にHow/Measureを配置。矢印や線を追加して関連性を示すことで、完成度が上がります。
2-3. タートル図作成のコツ・注意点
-
複雑化しすぎない
あまりに詳細な要素を全部盛り込むと、かえって視覚的にわかりにくくなる。大枠の要件をまずまとめ、必要なら別途資料(手順書やマニュアル)に詳細を記載して連携させるとよいです。 -
担当者を巻き込む
現場のオペレーターやリーダーを交えて話し合うことで、実務と図の乖離を防げます。もし図上で「実際の工程と違う」という意見が出るなら、そこに改善の糸口がある証拠なので大切に扱いましょう。 -
標準化・共有
作ったタートル図を紙やExcelで保管して終わりにせず、社内ポータルやクラウドなどで全員が参照できるようにする。教育や監査の場でも活用することで、プロセス理解を全社に広める効果があります。
2-4. スケーラブルな運用
タートル図は一度作って終わりではなく、定期的に更新するのが基本です。工場の工程や設備が増えたり、顧客要求が変わったりした際には、インプットやアウトプット、方法や指標も変わる可能性があるからです。たとえば新しいロボット導入や新検査規格の導入があれば、その都度タートル図に反映させ、古い情報とのギャップをチェックしておきましょう。こうして継続的に改善・修正するプロセスが品質や生産性を保ち、DXへ繋げる原動力となります。
3.タートル図活用のメリットとDXへの応用:実例・導入の流れ
タートル図は製造業が抱える課題(例えば、効率的な品質保証、規格対応、DX推進など)に対し、「プロセスの可視化と要素整理」という形で具体的なソリューションを提供します。ここでは、タートル図が現場に浸透した際のメリットや、DXと組み合わせる活用例、そして導入の手順をさらに掘り下げます。
3-1. タートル図活用の具体的なメリット
-
品質不良や手戻りを防ぐ
タートル図でプロセス要素を網羅的に洗い出すことで、「必要な人材は確保されているか」「設備や工具は適切か」「作業手順は明確か」「評価指標は妥当か」がセットで確認できるため、見落としによるトラブルが減少します。たとえば検査工程のタートル図を作れば、「どの測定器が必要か」「不良基準は何か」を可視化し、間違った道具や基準で検査するミスを防げます。 -
内部監査や顧客監査への対応がスムーズ
ISO 9001やIATF 16949の監査時には、各工程の責任・方法・評価指標などを説明する必要があります。タートル図を用意しておけば、プロセスアプローチでの説明が一枚の図で済むため、監査員へのプレゼンテーションが効率的に行えます。さらに、顧客監査でも「この工程はこの担当者が、この設備と作業手順で行っていて、品質指標はこれです」と即座に示すことで信頼度を上げられます。 -
教育・引継ぎが容易になる
新人や異動者が工程を理解する際、文字だけのマニュアルよりもタートル図の方が概要をつかみやすいです。誰が何を使い、何をアウトプットしているかが一目で分かるため、短期間で現場に溶け込む手助けになります。ベテラン社員が持っていたノウハウを文書化し、図示することで技術継承もスムーズになります。 -
自動化・デジタル化の検討に役立つ
DXを導入する際、どの工程でIoTセンサーを設置し、どこにロボットを導入するかなどを考える上で、タートル図の視点が非常に有効です。たとえば「この工程にはどんなリソースが必要で、評価指標は何か」という整理から、「ではIoTでこのデータを取得すれば工程を数値化できる」というアイデアが生まれる、という流れがあります。
3-2. タートル図とDXの親和性
タートル図で整理したプロセスは、DXの取り組みと相性がよいといえます。DXでは、「データに基づく最適化」「全社的なプロセス連携」「迅速な意思決定」などが目指されますが、タートル図によりプロセスと関連要素をはっきりさせておくことで、DX施策をどこに、どのように入れていけば効果が出るかを見つけやすくなります。
-
工程ごとに取得すべきデータが明確に
タートル図で「指標(Measure)」を挙げているので、その指標をリアルタイムに取得するためにIoTやクラウドシステムを導入する設計が容易。 -
属人的管理をシステム化
図に書かれている「Who/With what/How」をデジタルシステムへ落とし込めば、生産管理システムの工程定義や権限設定に対応できる。 -
継続的改善とPDCAの基盤
DX成功の鍵は「プロセスを見える化し、データを分析し、改善アクションを回す」こと。タートル図は見える化の最初の段階を助け、データ活用のPDCAを推進しやすくする。
3-3. タートル図導入の手順
-
対象プロセスの選定
すべての工程を一気に取り上げると膨大な作業になるため、問題が大きい工程や監査で重点的に見られる工程など、優先度が高いところから始める。 -
現場ヒアリングとドキュメント収集
実際の作業者や現場リーダーにヒアリングし、既存手順書やQC工程表などを確認して、必要な要素(インプット、アウトプット、リソース、手順、指標)を整理。 -
タートル図の試作とレビュー
担当者が初稿を作り、関係者全員でチェックする。現場の実態と合わない部分や重複を見直して完成度を高める。 -
全社への共有と更新サイクル
作成したタートル図を共有し、運用を通じて出てきた変更点を適宜反映。定期的な見直しを行い、最新の状態を保つ。
3-4. メンテナンスと活用事例
タートル図は一度作って終わりでなく、新しい設備や工程変更があれば随時アップデートが必要です。たとえば、新しい検査機を導入すれば「With what」に追加したり、新たな品質指標を設定すれば「Measure」の欄を修正するなど、運用とともに進化させることで実用性が維持されます。現場では、以下の活用事例が報告されています。
-
不具合改善プロジェクト: 不良率が高い製品の工程タートル図を作り、「どの装置がどのような作業を担当しているか」を可視化。問題工程を特定し迅速に対策を打てる。
-
新人教育プログラム: 入社直後のスタッフに対し、各工程のタートル図を使って「どこに何があり、どんな手順と検査基準があるか」を学ばせる。紙マニュアルだけより理解が早い。
-
監査・顧客対応: ISOや顧客監査の際、タートル図を提示して「どのように品質を管理しているか」を説明。監査員からも「現場がプロセス管理を理解している」と高評価を得る。
こうした運用事例を見ると、タートル図は特定の部門だけでなく、全社横断のコミュニケーションツールとしても機能していることがわかります。DXで仕組みを電子化していく際には、ぜひクラウドや生産管理システムにタートル図の要素を紐づけ、デジタル上でも参照しやすい状態にするのがおすすめです。
まとめ
「タートル図」は、製造業の多様な工程をシンプルかつ体系的に可視化し、品質や生産性を高めるための効果的な手法です。プロセスのインプット・アウトプット、必要な設備・人材、作業手順や指標などを図示することで、抜け漏れを防ぎ、改善ポイントを明確にします。近年のDX推進の流れでは、タートル図を入り口として工程を整理し、そのうえでIoTやAIなどの先端技術を取り入れるケースが増えています。こうしたステップを踏むことで、属人的だったノウハウがデジタルデータと組み合わさり、品質やコスト、納期などの管理が大幅に効率化できるわけです。
ただし、タートル図は単なる図表で終わらせず、実際の運用フローに落とし込むことが大切です。定期的に更新し、現場が活用しているかを確認しながらPDCAを回すことで効果を発揮します。そして、より高度なデータ活用や工程管理を行うには、生産管理システムとタートル図を連携させるのが理想的です。なかでもおすすめしたいのがクラウド型生産・販売管理システム「鉄人くん」です。「鉄人くん」はクラウド型の生産管理システムとして、受注から在庫・工程・品質・販売管理までを一括で運用でき、タートル図で整理した各プロセスや要素をシステム上に紐づけることで、担当者と作業内容、指標をリアルタイムに見える化できます。
「タートル図でプロセスを可視化し、鉄人くんで管理・分析する」流れを作れば、製造業がDXを加速するうえで最適な基盤となるでしょう。現場スタッフの業務負荷軽減や納期順守率向上、品質不具合の早期発見など、多くのメリットが期待できます。