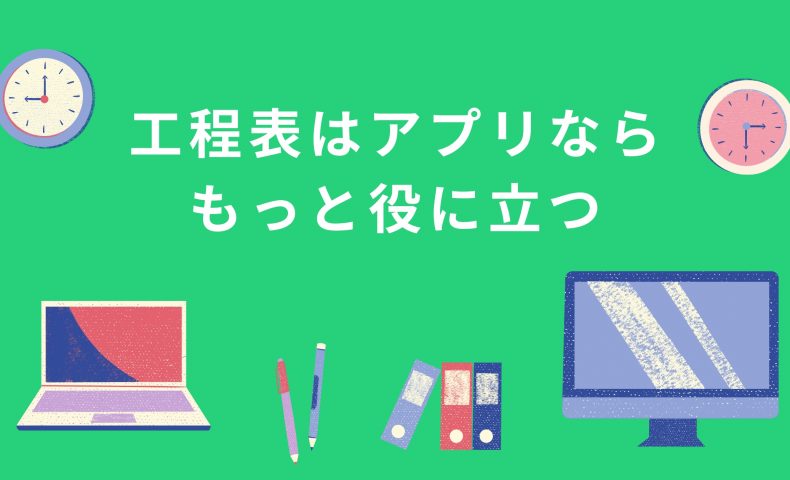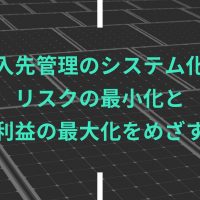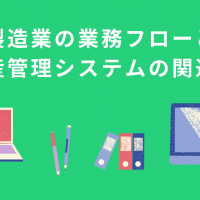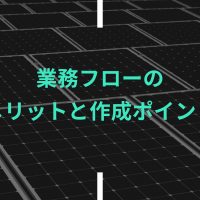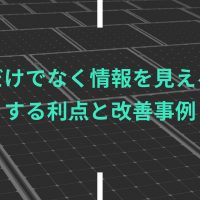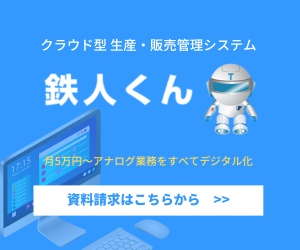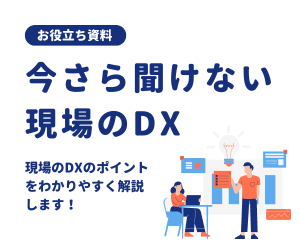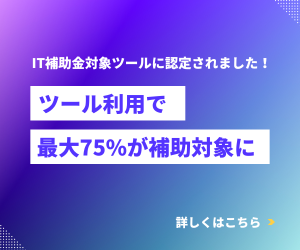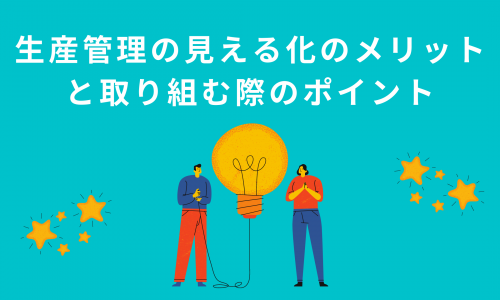製造業において従来、工程表は一部の人にしか見られないものでしたが、昨今はDX化などに伴い共有できるデータとして進化しています。工程表をアプリで作成することで、作業が標準化されたり、再現性が高く品質の高い製品へつなげられたり、リードタイムも把握しやすくなるなどメリットが見込めます。
この記事では、製造業での工程表の役割とDX化にアプリが向いている理由について、いくつかのポイントに絞って解説します。
工程表の役割と必要とされるポイント
工程表とは工程管理表を略した名称です。製造業では、原材料から製品を完成させ、販売できるようにするには、さまざまな工程を必要としますが、工程表を使えば、見通しが効くようになります。ですから、モノづくりの世界で工程表は、古くから使用されてきています。DX化されても、工程表の役割そのものは変わりませんが、より利便性が高くなります。
ここでは、工程表の役割とそのポイントをご紹介します。
工程表の役割
工程表の役割は、主なもので5つあります。それぞれ簡単に説明しましょう。
- 工程の見える化・各工程どうしの関係性把握
工程表があれば、どの工程で何をおこなうのかが見通せ、前後関係もわかりやすくなります。こうすれば、抜けや漏れが発生しませんし、作業者にとっては、担当する工程への理解が深まり、意欲や責任感の向上もはかれます。
- リードタイムの把握・時間短縮
製造業でのリードタイムとは、商品の発注を受けてから納品されるまでの期間のことを指します。
注文が滅多にない製品では、リードタイムのなかに、原材料をメーカーに発注し納入されるまでの原材料メーカーのリードタイムが含まれます。
工程表があればリードタイムの把握とともに、どの工程に時間がかかっているのかを判断しやすく、時間短縮もしやすくなります。
- 工程所要時間の把握
工程表があれば、工程ごとの所要時間が一目でわかります。たとえば、前処理工程や試験検査など、製品の流れとは違う工程の時間管理は、専門性が要求され、なかなか流れが把握しにくいものです。しかし、工程表があれば製品のどの工程から開始され、どの工程までに終了していなければならないのか、時間の感覚を持ちやすく、わかりやすくなります。
これは、前処理待ちや試験待ちの余剰時間を前もって把握でき、人員配置などを対応できる利点とともに、前処理や検査の工程からしても、製品の流れが把握でき対応可能になるという両面からの利点を持ちます。
- イレギュラー対応
工程表があれば、トラブルがおきた際も見通しがつきやすく安心です。どの工程が進まないのか?それとも能力が落ちて遅延するのかなども、工程表があれば対応しやすくなります。またアプリであれば、修正も簡単です。
トラブルが発生した場合、もっとも消耗するのは先が見えないことではないでしょうか?故障はいつ治るのか?製品は間に合うのか?などの不安を、工程表は見える化して楽にしてくれます。
- コスト削減
工程表では、各作業を段階ごとに見える化します。このときに、合理化やまとめ作業などのコスト削減につながることが少なくありません。
頭の中だけでは、わからなかったコスト削減の種が、工程表から見えてくるのです。
工程表に必要なポイント
説明してきたように、工程表は製造業にとって便利な道具になってくれます。利用しやすくするためには、以下のポイントを明確に記載しなければなりません。ここからは、工程表に必要なポイントを解説します。
- 正確な工程区分
製造業にとって、工程区分とグループ分けは区別する必要があります。製造工程というグループであったとしても、その中の作業ごとに工程を分けなくては、内容がわからなくなるでしょう。
参考として医薬品や食品でよくある製造工程の分類例を示します。
- 製品を作る準備作業(秤量、洗浄、濾過、裁断など)
- 製品を作る
- 容器を準備する
- 製品を容器に入れる
- 蓋をする
- 殺菌や滅菌をする
- 箱に入れる
- 輸送用の箱に入れる
- パレットに積む
このように、製造といってもそれぞれ専門性が違いますし、まとめて作業するのか、流れ作業なのかも違います。管理がしやすいように、客観性を持った工程分けが必要です。
- 担当範囲
工程分けをしたら、今度は担当範囲を明確にします。担当があいまいな工程があれば、トラブルの元です。各責任者も明記します。
- 時間の流れ
時間の流れについての記載も重要です。とはいっても、いつも同じ時間で作業するのは難しいので、標準作業時間を設定します。ここで大切なのは、気づきが放置され大きな問題にまらないように、ギリギリの時間設定を避けることです。
トラブル実績がわかる場合は、ある程度チョコ停なども考慮した時間設定にしましょう。
この時間設定を作業標準時間と呼ぶ場合もあります。
作業標準時間は「標準的な技能の習熟度合いを持つ作業者」が「定められた作業手順で標準的に動く機械を用いて作業」した「標準時間(ST)」に、「余裕時間」を加算した時間です。
作業標準時間は、リードタイムを決定する重要な指標ともなります。
- 作業内容
当然、それぞれ工程の作業内容についても工程表に記載されます。どこまで詳細に記載するかは用途によりますが、製品全体の工程表ではおおまかに、工程ごとにそれぞれの詳細を記載する工程表では詳しく記載され、チェックシート代わりに使うこともあります。
- 動線
工程表には、原材料が製品になるまでの動線も大切です。一般に原材料は、最終的にひとつの製品として集積されていきます。その工程内で原材料が、どこから中間製品になるのか?中間製品の段階によって名称が違う場合は、それぞれどこから名称が変化するのか?最終製品となるのはどの段階なのかについての記載も必要です。
それぞれの前処理が必要なら、その前処理ごとに工程表が作られ、製品の工程表に集積されることが多いようです。
ガントチャートとは
工程表は工事現場でも使われますが、いろいろな工程表を使いわける工事現場に対して、製造業では、ガントチャートやそれを応用した工程表が使われることが、ほとんどです。
ガントチャートは、縦に作業内容とその開始日と完了予定日を並べた表に、帯状に期間や進捗が示された工程管理表です。製造業では、同じ製品では、同じガントチャートを作成します。このまま製品の標準書的に使用されることも多いようです。この場合は、ガントチャートをロットごと、バルクごとに作成し、各作業開始及び終了時にチェックし、進捗状況を管理します。
ガントチャートのメリットは、直感的に工程を見通せて進捗がわかることです。また、視覚情報が単純なので情報共有しやすいこと、トラブルの際に対応が早いことなども便利で、広く製造業で使用されています。逆にデメリットとしては、作業量がわかりにくいことや、優先度合いが、わかりにくいという点があります。
以前、ガントチャートのデメリットのひとつに、紙媒体で作成している頃には、作りにくい、修正しにくいという点もありました。しかし、現在では、アプリが一般化した結果、作成や修正は楽になってきています。
製造業の工程表の特徴
製造業の工程表は、工事現場などとは違う点があります。それは、ロットや製造番号ごとに作成すること、そして工程ごとに作成して最終的に一つの工程表に集約していくこと。また、チェックシートを兼ねる場合が多いことです。
通常の製造業の場合、注文に応じて同じ製品を何度も作るので、何度も同じ書式を使用します。修正前後には、版の管理に注意が必要です。特に、ファイル保存によって同じファイルが複数作られてしまうエクセルなどでは、どれが原本なのかがわかるように管理しなければなりません。一言で版管理といっても、小さな更新を抜けなく管理するのは、なかなか骨が折れる仕事と言えるでしょう。
工程表のDX化とは
現在、全産業でDX化がすすめられています。製造業も例外ではありません。工程表もDX化が進み、ずいぶん便利になってきました。ここでは工程表をDX化する利便性や、おすすめの方法を紹介します。
DX化と2025年の崖とは
DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略語です。AIやIoTなどを活用して、ビッグデータの利用を進めることで、ビジネスのデジタル化に革新を起こすことを指します。日本では従来のコンピューターシステムに依存する体質などが理由で、DX化が進んでいないのが実情です。しかし、DXを推進しないまま、システムが刷新されなければ、日本は2025年からは、毎年、年間最大12兆円の経済損失が生じ続けるといわれ、これを「2025年の崖」と呼んでいます。経済産業省やデジタル庁を中心に、DX化がすすめられています。
工程表はDX化すると利便性が増す
工程表がDX化すると、とても便利です。
まず、DX化すれば、同じひな形を使いやすくなり、版管理が簡単になります。デジタル化すれば、小さな違いも見逃さずにすみます。今まで読み合わせで時間をかけていた部分を簡略化できます。また、工程表の進捗が明確化されるので、リードタイムも計算可能です。クラウド型であれば、出先であっても、顧客に納期を明確に伝えることができます。
また、ペーパーレスになれば、清浄度が高い区域でも対応しやすいという利点もあります。
工程表のDX化にはクラウド型のアプリがおすすめ
工程表のDX化には、アプリがおすすめです。アプリは、コンピューターシステムの専門家が作成し、アップデートしながら使っていくクラウド型のシステムです。アプリを使えば、タブレットや携帯でも、同じ工程表が共有できます。
そのため、工場外にいる営業担当者にもリードタイムを加味した納期が把握できます。
アプリなら版管理も安心です。他の名前で保存するという前提が、そもそもありませんからうっかり別の名前で保存して混乱するなどのミスが防げます。
また、近年ではアプリのセキュリティについても、クラウド型の信頼がアップしています。なぜなら、最新の情報を手にできるプロフェッショナルがチーム制で、セキュリティを保守しているからです。複数のデータセンターにバックアップもあり、天災にも強いシステムになっています。
まとめ
工程表は生産全体を把握するのに重要な役割を果たしています。見える化され、共有化された工程は、品質・納期・効率を向上させ、クライアントやユーザーを満足させる製品を生み出します。
工程管理は情報の共有性の高いプログラムとして利用できるアプリがおすすめです。製造業専門のクラウド型生産管理・在庫管理システム「鉄人くん」なら、製造業にあった仕入先管理が組み込まれていて、スマホでも確認できます。生産管理システムや販売管理システムもパッケージされていますから、より効率的に工程表を使って効率アップも可能です。一度検討してみてはいかがでしょうか?
また、トライアルキャンペーンも実施していますので、システムの導入を検討してみたいとお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。