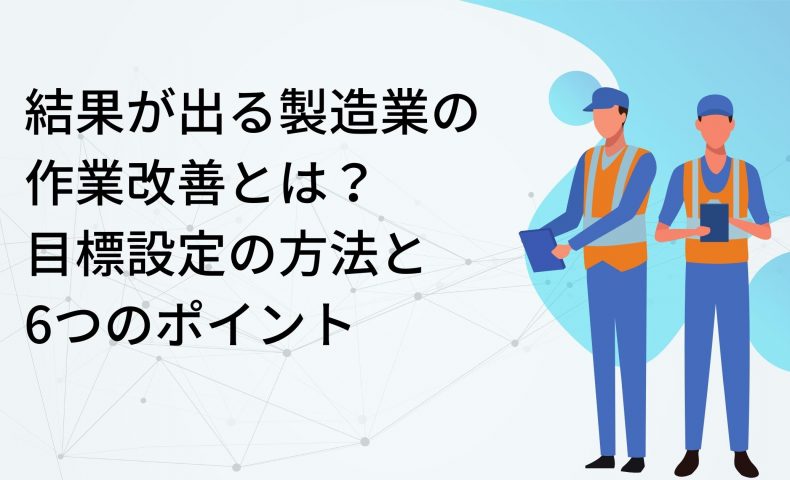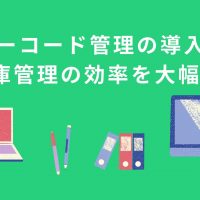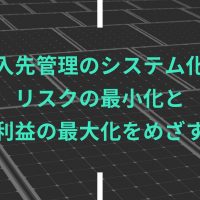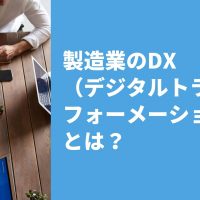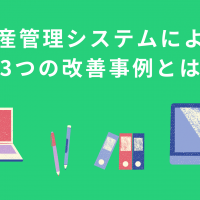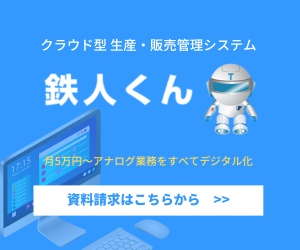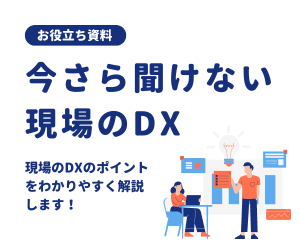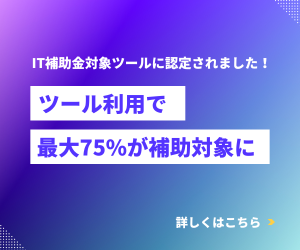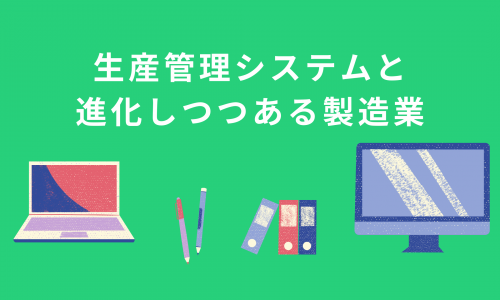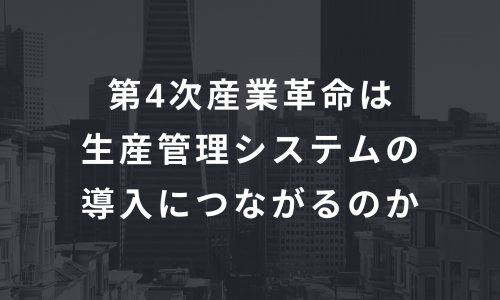より良い工程、よりよい動線、そしてコスト削減。作業改善は製造業にとって「あたりまえ」であり、必須の活動ですが、作業改善の結果が出ているでしょうか?もし、効果が作業時間に見合わないようなら、やり方を見直す必要があるかもしれません。
そこの記事では、製造業の作業改善の現状を知るために、チェックシートをご用意しました。そして、結果を出す目標設定の方法と6つのポイントをご紹介します。この記事で、停滞気味の作業改善に結果を出していきましょう。
作業改善が停滞していませんか?
あなたの職場では作業改善が停滞していませんか?作業改善の結果を出す方法の前に、職場の作業改善の停滞度を振り返りましょう。以下にチェックシートを用意しました。あてはまるものが何個あるか数えてみてください。
【作業改善停滞チェックシート】
- 言われたところをやればいい
- 作業改善には意味がない
- 気になっているけれど手が出せない場所がある
- 作業改善をはじめると、こだわって時間を忘れる
- 先取り作業が本作業を圧迫している
- 自分ばかりがやっていると不満だ
- 改善した所の改善はおこなわない
- 監査のとき対応に追われる
- 他業者が改善に成功した方法を、そのまま流用する
- 誰がなにをしているか明確化されていない
- 「チョイ置き」になっているものがあるが、誰も気にしない
- 改善しても守らない人がいて、なし崩しになる
- 作業改善をしている人が大切にされていない
- 頑張っても誰も見てくれていないように思う
- あいさつや声掛けができていないと思う
【あてはまる数】
0~3個:作業改善はうまく機能しているようです。
4~8個:作業改善が停滞し始めています。いまのうちに対策を。
8~12個:作業改善は危機に瀕しています。グループで問題を話し合って。
13~15個:作業改善は瀕死状態。 形だけで時間の無駄になっているかも。
いま作業改善が停滞していなくても、停滞リスクはあるものです。その兆しを見極めるために活動の停滞する兆候、停滞を防ぐ方法をご紹介します。
作業改善の停滞は目的を見失うことから始まる
作業改善を始めた時は、「この仕事を、よりよいものにしよう」という思いが、多かれ少なかれあるものです。
では、それがなぜ停滞してしまうのでしょうか?それは、どこに向かうかわからなくなり迷ってしまうからです。
作業改善が停滞している職場は、人間関係や時間のなさ、怠惰などの雑草に覆われて、作業改善の目的が見えなくなってしまっています。
停滞している職場では、再度作業改善の目的を確認する必要があります。現在、作業改善がうまく機能している職場でも定期的に目的を確認し、停滞するのを防ぎましょう。
作業改善の目的はなにか?
結果の出る作業改善が実施できている企業は、作業改善の目的を知っています。
作業改善の目的は主に以下の3つです。
- 製品の品質向上
- 不安全作業の解消
- 作業の効率化
目的に沿った目標であれば、結果がでやすい
目的にそった目標で実施されていれば、その成果は時間や安全などの利益を生み、評価されるものになるでしょう。評価は自尊感情のもとになり、活動そのものが教育の意味を持ちます。
改善が製品の品質向上につながれば、製品の信頼性は向上し、仕事にプライドを持てます。不安全作業の解消につながれば、安心して作業できるでしょう。また、作業の効率化は、余裕をもたらすでしょう。このように、作業改善は作業そのものだけでなく精神面での快適性を向上させ、より一層の作業改善のモチベーションアップになるのです。
ですから、作業改善の小さなトラブルも乗り越えやすく、結果が出やすい状況にあります。
作業改善が目的に沿っていれば良い流れができ、より良い状態へと変化していきます。
作業改善を流れに乗せるには目的に沿った目標を明示する
逆に作業改善を流れに乗せたいなら、まず目的に沿った目標を明示するのが効果的です。
最初は、あまり大きな目標にせずに達成の喜びを味わうのがおすすめです。
もし大きな目標を立てたいのなら、そこまでの道のりを細分化して目標を設定するのが良いでしょう。
目的を明示して目標を設定することで、作業改善の土台ができる
目標を設定するときは、目的も明確に示しましょう。現状から目的までを見通せることで、アイデアも生まれやすくなりますし、迷走を防げます。
目的に沿って設定される目標の具体例
| 目的 | 目標 |
| 製品の品質向上 | ・クレームが多い項目を改善する
・製品のばらつきを少なくする ・不良品を少なくする ・製品を使いやすくする ・集積データの統計・解析 ・外注品の品質向上 |
| 不安全作業の解消 | ・高所作業を減らす
・可動部分に作業者が入らずにすむようにする ・作業動線のリスクを減らす ・危険物の取り扱い方法を見直す ・ヒヤリ事故を減らす ・保護具の整備 |
| 作業の効率化 | ・機械の停止を防ぐ
・煩雑な作業の洗い出し、改善 ・ボトルネック(他工程を待たせる)工程対策 ・データ集積の効率化 ・人員配置の見直し ・作業員のスキル向上 ・修理に使用する物品のリスト化 |
結果を出す作業改善を行う6つのポイントとは
目的に沿って目標を設定したら、ポイントをおさえて作業改善を進めましょう。ここでは製造品目を問わず重要な6つのポイントをご紹介します。これらは、作業改善が停滞している企業では、できていないことが多いものです。再点検し、再構築することをおすすめします
ポイント1:目標を明確にする
① 数値化する
製品の品質向上を明示できる指標です数値できる目標は数値化する方が、誰にもわかりやすい目標になります。わかりやすい目標があれば、作業改善取り組みやすくなります。数値化できる指標の例をご紹介します。
製品の品質向上に関する指標
- 工程能力指数
- 製品の不良率、不良数
- 原材料の不良率、不良数
- クレーム件数など
不安全作業の解消に関する指標
- 労災件数
- ヒヤリハット報告数
- 危険個所
- 危険作業の数
作業の効率化
- 停止時間
- スキル取得人数
- 物品の購入金額
- 廃棄数
② 目標となる状態を明確に示す
目標の明確化には、数値だけでなく状態の明確化も有効です。これは改善したいことはあるけれど、作業改善方法が決まっていない場合のブレインストーミングにも使えます。
まず目指したい状態を考えて、作業改善に方法について多方面からアイデアを出します。この場合、荒唐無稽で実現不可能と考えられる方法も、バカにせずにアイデア出しするのがコツです。最も有効な対策は、実現不可能と考えている方法と現実の方法の間に存在することが多いのです。
そして有効な方面の対策に関して数値目標を考えれば、最初から数値目標を上げるより自由度の高い作業改善ができます。
これは、うまく対応方法がみつからない場合などに、とても有効な方法です。
ポイント2;基本を押さえる
頭の中で考えた素晴らしいアイデアも、現場で実施すると思わぬ障害や不具合があるものです。行き詰った時も「基本に戻る」ことで活路を見出せます。
また、作業改善以前に「作業の基本」を徹底することも、作業改善につながります。
- 枝葉末節でなく本筋を改善する。
- 現場主義:その場所で考える。
- 行き詰ったら5S(整理・整頓・清潔・仕組み・習慣)活動に戻る
- ひと仕事ひと片づけ:出したものは戻すを徹底する。
- 終業時には、次の朝に気持ちよく仕事が始められるようにする。
- 作業中に浮かんだアイデアを基本に活動する。
- お互いに、あいさつや声掛けをし、風通しを良くする。
ポイント3:作業を見える化する
見える化は、「原因がよくわからない」問題が発生しているときだけに利用するのではありません。どんな問題でも見える化すれば、思ってもいなかった要因が発見されます。
見える化といっても、時間や作業動線、担当など様々です。タイムテーブルも工程全体、各作業者、作業ごとなど目的にあわせる必要があります。
ポイント4:組織の性格を見定めて改善する
組織は人が集まって作られています。ある組織で有効だった対策が、別の組織で有効に働かない場合もあります。他組織の作業改善の事例を導入するときは、組織の性格を考慮して進めましょう。
堅実なタイプが多い組織なら、スキマ時間の有効活用や先手仕事を使ったコツコツと積み上げていく方法が向いています。一方、元気があり勢いで進むタイプの組織なら、作業の連動、集中時間の導入など、チームワークを意識させるイベント的な作業改善が、大きな成果を生むでしょう。
また、作業改善は引き受けすぎる人が出やすいことも覚えておきましょう。不満が出ないように、それぞれの役割を与え、できるだけ多くの人に実施してもらいましょう。
ポイント5:完璧を目指しすぎない
作業改善を進めていくと、完璧の迷路に入ってしまうことがあります。完璧を目指しすぎると、枝葉末節に時間をかけることになり、逆に作業効率が下がる場合もあります。あくまでも作業改善の目的は、製品の品質向上、不安全作業の解消、作業の効率化です。すべてを完璧は必要ありません。
完璧の迷路に迷い込まないためには、①期間を設定してテーマを決める、②改善に夢中になりすぎない、③全体を見通す機会を設ける、③時間を決めて取り組むなどの方法が有効です。
ポイント6:DXを有効に使う
今までは不可能だった複雑な作業もデジタル技術によって簡単に実現できるようになりました。
デジタル技術を発展させた考え方がDXです。スマートスピーカーや自動運転車など、近年急速に実用化が進んでいるIoTや膨大なデータから学習して単純作業実施するAI、従来のネットワークより高速にデータが処理できるクラウド5GなどがDXを担っています。
製造業でも、製造機械そのものをデジタル化したり、大量の生産に関するデータを集積し単純作業を機械化したり、各事業所間で情報をやり取りしたりと、DXは作業改善に役立つ可能性を秘めています。
DXは、いままでの煩雑な作業を一足飛びに簡略化でき、計算や在庫、段取りの管理が格段に楽になります。製造業に大きな変革をもたらしますので、導入するときは慎重に選定する必要があります。
DXも作業改善として有効
製造業の作業改善で結果を出したい方に、目標設定の方法と6つのポイントをご紹介しました。目的を把握して目標を立て、6つのポイント(目標を明確化する、基本を押さえる、作業を見える化する、組織の性格を見定めて改善する、完璧を目指しすぎない、デジタル技術を有効に使う)は作業改善の基本です。
しかし、作業改善が停滞している企業では、できていないことが多いものです。再点検し、再構築することをおすすめします
製造業の作業改善に最適なデジタル化ツールの例として、株式会社ビジネス・インフォメーション・テクノロジーの提供している製造業専門クラウド型生産・販売管理システムの「鉄人くん」をご紹介します。
クラウド型生産管理システム「鉄人くん」は、製造業専門のシステムのため、製造業の作業改善にピッタリのシステムです。クラウド型で使いやすく、顧客満足度を向上させるシステムといえるでしょう。
作業改善に、システム化を利用する際には「鉄人くん」も選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?
また、トライアルキャンペーンも実施していますので、生産管理システムの導入を検討してみたいとお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。