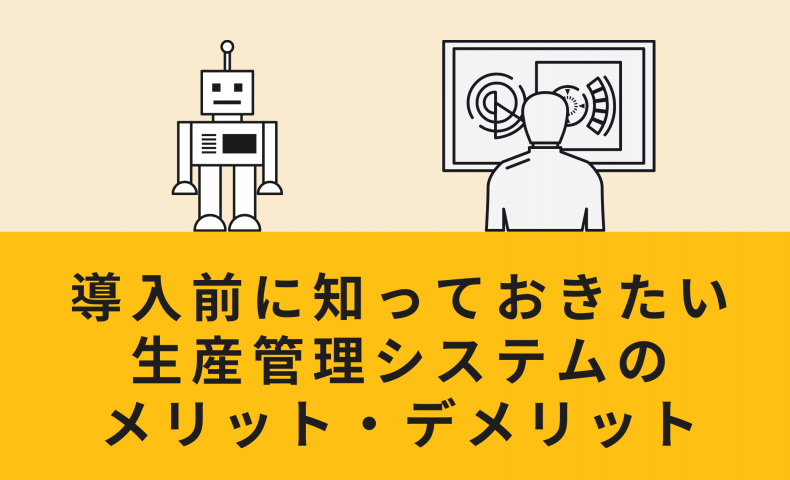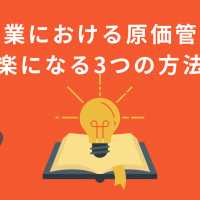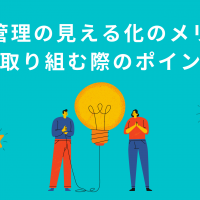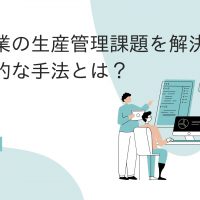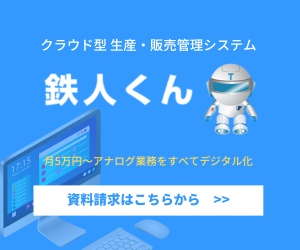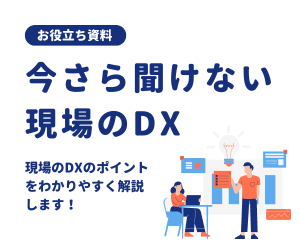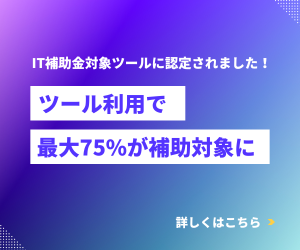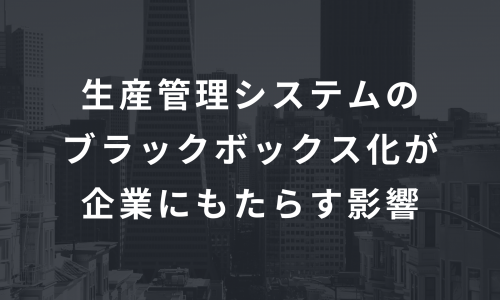製造業では、コスト削減や市場の変化への対応が求められています。また、時代の変化に合わせてこれまで以上に生産計画と管理を効率良く行う必要があります。そのため、生産管理システムを導入する企業も見受けられるようになりました。
しかし、生産管理システムを導入する注意点がよくわからないと悩みもあります。そこで、今回は、生産管理システムのメリット・デメリットについてみていきましょう。
生産管理システムの特徴
生産管理の特徴として、手動で行っていた生産管理業務を自動化し、製造業におけるムリ・ムダ・ムラの軽減が可能です。例えば、以下のような3Mの要素は全て生産管理システムを活用した場合に、解消できる可能性が高いといえます。
・原価管理にリソースを使っている(使っても計算が合っていない)
・人材や部署に対する負荷の把握ができていない
・商品の品質管理ができていない(出荷後も含む)
製造業には、製品を作った際の責任があるだけでなく、3Mが発生するほど利益の獲得が難しくなります。実際に、製品の製作が上手くいっても内部管理ができていない場合、売上の確保は難しいでしょう。とくに、何にどのくらいのコストをかけたのか把握できていない場合は、会社の経営そのものが次第に苦しくなっていくと想定されます。
しかし、生産管理の導入によって、状況を変えることが可能です。勤怠管理や原価など、人材に頼っていたほぼ全ての計算を自動化できます。工程管理をできる人材がいなければ、その代わりを担うことも不可能ではありません。そのため、生産管理システムは、3Mを軽減し、工場内の効率化を進めるシステムだといえるでしょう。
生産管理システム導入のメリット
生産管理システムは生産計画の策定だけでなく、人員や設備管理を効率化できます。そのため、製造現場における生産性を向上させることが可能です。ここでは、導入時にもたらされるメリットについて解説していきます。
生産状況を把握でき、工数削減につながる
工程管理機能があるため、 生産の進捗状況を素早く把握できます。例えば、生産現場ごとに負荷の偏りがある場合、効率的に製品の生産が行えません。また、人的なミスや機械トラブルなどにより、どこかの工程で遅れが出る可能性もあります。
しかし、生産の進捗状況がわかれば、稼働率なども可視化できるため、遅れている工程や負担が偏っている工程へのサポートを迅速に行えます。また、生産管理を手書きや手入力で行っている企業であれば、ハンディ端末などでの作業記録に切り替えることで、工数の削減につながるでしょう。
また、製品別や担当者別などの生産実績データを自動で集計できます。生産管理システムによって工数削減が可能となるため、業務の効率化に結びつきます。
在庫管理を適切に行える
在庫管理の見える化は、今後企業が生き残っていくために必要です。大量生産を行っても売れ残った場合は、在庫を抱えることになってしまいます。また、部品などを作成する企業においては、取引先の指定した個数以上の商品は無駄になります。
加えて、在庫管理を紙などのアナログ的管理手法で行っていた場合、リアルタイムで把握するのは困難です。場合によっては、経験値や勘に頼るといった方法を取っている企業もあるでしょう。
しかし、生産管理システムでは、製造過程を含めた生産ラインの情報を可視化して共有できます。そのため、在庫情報や販売情報はシステムにアクセスできる人材であればだれでも把握が可能です。リアルタイムで在庫状況を把握できれば、在庫欠品などを未然に防止し、必要最低限の仕入れだけで済ませることが可能です。
また、営業を行う際にも取引先のスケジュールに合わせるといった柔軟な対応が可能となるため、提案や仕入れもスムーズに行いやすくなるでしょう。
原価管理や利益率の改善に繋がる
生産管理システムを用いることで、簡単に原価のシミュレーションを行えます。製品ごとや取引先ごとの原価計算も行えるだけでなく、導入するシステム次第では概算と実績の原価一覧表を出力することで、その差異を確認できます。
そのため、生産管理担当者の方が素早く正確に原価管理を行えるため、見積もりをスムーズに出せるなど、他の工程にも良い影響を与えます。
製造原価をリアルタイムで把握できれば、利益率が適正なのか分かります。適正でない場合、価格の再検討や品質の標準化など改善に向けたアプローチを行うことも可能です。
特に、利益率は経営に直結する数字です。過去と比較して、利益率が減少している場合は生産利益と対比したうえで調整を行う必要があります。
生産スピードが上がる
生産工程をコントロールしつつ、あらゆる業務の効率化が可能となります。例えば、生産に関わる部門間の情報共有を円滑に行えるだけでなく、在庫管理を適切なタイミングで仕入れることでタイムロスがなくなります。
一定規模の中小企業では、工程管理においてもそれぞれのリーダーが存在し、それぞれに確認を取らなければコミュニケーションだけでなく、状況が把握しづらいといったケースも多いでしょう。
しかし、生産管理システムの採用によって、生産における情報共有に時間を割かなくなるため、より人材が必要な戦略や商品設計に時間を使えるようになります。AIやシステムが全てをサポートできる訳ではないものの、機械と人材の区分けをより鮮明にできるでしょう。
生産管理システム導入によるデメリット
ここでは、生産システムの導入時に起きうるデメリットについてみていきましょう。とくに、目的意識のないシステムの導入は失敗につながる可能性があります。
また、生産管理システムを導入する場合、月額か初期費用が必要となる点はデメリットだといえます。大規模なシステムであるほど高額になるだけでなく、今までの生産工程に対して大きな影響を与える点は把握しておきましょう。
対策としては、コスト負担の増加が気になる場合はクラウド生産管理システムから導入をスタートする方法があります。例えば、原価管理などから自動化できるため、徐々に適用する範囲を広げることで失敗するリスクも最小に抑えることが可能です。
また、コストを度外視してもいい場合は、サービス提供事業者との徹底的な話し合いが必要になります。自社の課題を入念に検討したうえで、どの課題を解決したいのかを明確にしなければなりません。
加えて、導入した場合には従業員に対して研修などの手間が発生するケースも想定されます。しかし、課題を解決できる場合には、ある程度の負担が一時的に増加したとしても、それ以上のメリットがあることを入念に伝えることで不満を減少させられます。
まとめ
h生産管理システムは、導入に成功すれば、企業の生産活動に対してプラスの影響を与えるといえるでしょう。とくに、管理そのものができていない、一部の作業にリソースが掛かりすぎている場合はシステムの導入によって、課題を解決できるでしょう。
そのうえで、コストが掛かる点や課題をる明確にしなければ、効果を感じにくい点などデメリットも把握しておくことが大切です。
クラウド型生産管理システム「鉄人くん」は、
わかりやすい画面と手厚いサポートで、生産管理システムが初めても企業でも使いやすくわかりやすいのが特徴です。
生産管理システムの導入を検討してみたいと思った方は、こちらからお気軽にお問合せ・ご相談ください。